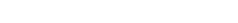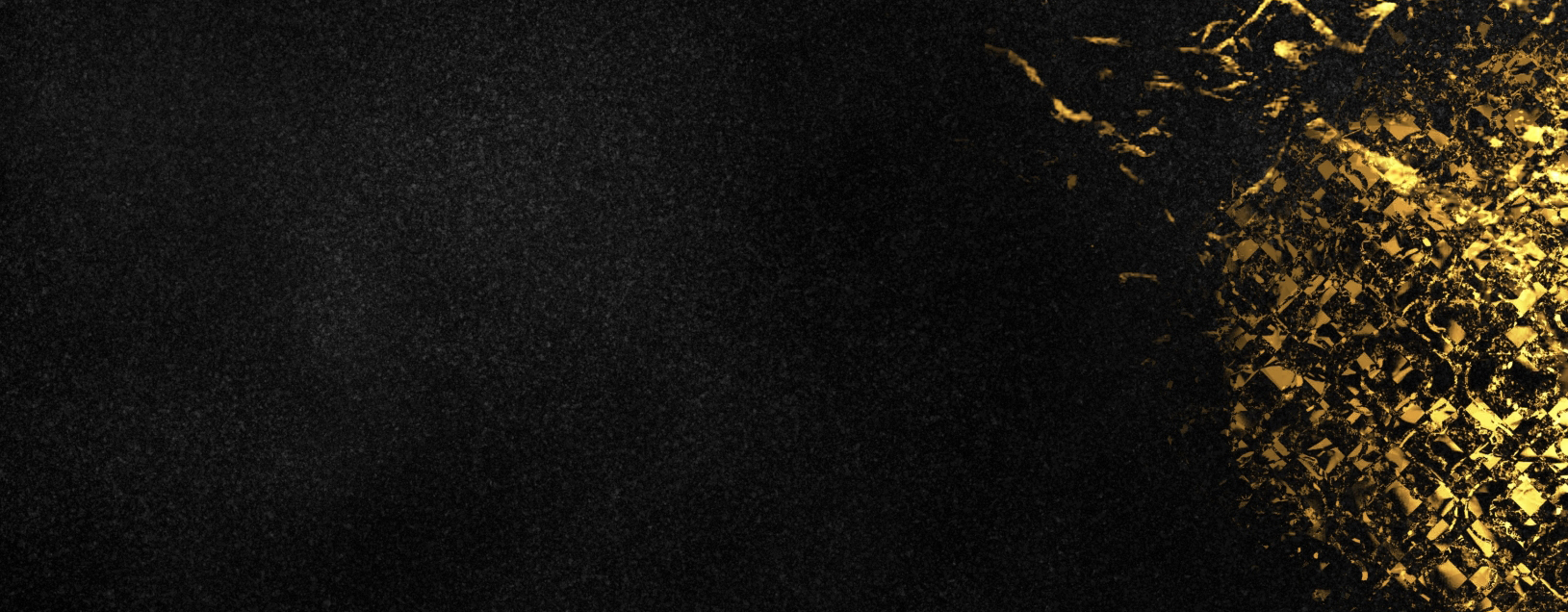
お知らせnews
2023.02.14
◇ 作家紹介 ◇ 田村耕一
田村耕一(たむらこういち)
1918年 栃木県に生まれる。
1945年 京都にて陶磁器の本格的研究を開始し、富本憲吉に師事する。
1948年 栃木県佐野市へ戻り、赤見窯の築窯に加わる。
1950年 濱田庄司勧めで栃木県窯業指導所技官となる。
1976年 東京芸術大学教授に就任し母校での後進の指導にあたる。
1986年 「鉄絵」で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
鉄絵とは酸化鉄(鉄に生じるサビの成分)で下絵を描く技法であり、素焼きした素地に絵を描いて、その上に釉薬をかけて焼成します。
田村耕一は地元の人形店に生まれ、幼少のころから人形や鯉のぼりの絵付けでその画才を磨いたといわれます。はじめ画家志望でしたが、大学在学中に陶芸の基礎を学び興味を持ち、21歳のころ益子で活躍していた濱田庄司を訪ねています。
戦後は京都に赴き輸出陶磁器のデザイン研究所で富本憲吉の指導を受け、2年間で色絵磁器を学び地元に戻ります。本格的に作陶活動を始める傍ら、赤見窯の創業に参画します。 その数年後、濱田庄司の薦めで栃木県窯業指導所の技官になっています。
初期の頃は黒色と黄褐色の二種類の鉄釉を用い、蝋抜きや筒描きによる草花文様の作品を発表して高い評価を得ます。その後、刷毛目を施した上に勢いのある筆描きで鉄絵の文様を表し、銅彩を併用して色彩に変化を与え、さらに青磁釉を用いて重厚さを表現するなど鉄絵を基としながら数々の技法を加えて表現内容を豊かにし、高い技術性を持つ陶芸を制作し、これまでにない新たな作風を生み出しました。
田村耕一は酸化鉄を用いて陶器に文様を描く「鉄絵」の技法を生み出し、陶芸界に新たなジャンルを確立させ、その作品は多くの陶芸愛好家を魅了し続けています。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。