近藤悠三は、その染付技法を伝統的な枠組から新しい芸術表現へと昇華させました。
その染付は「近藤染付」とも呼ばれる。
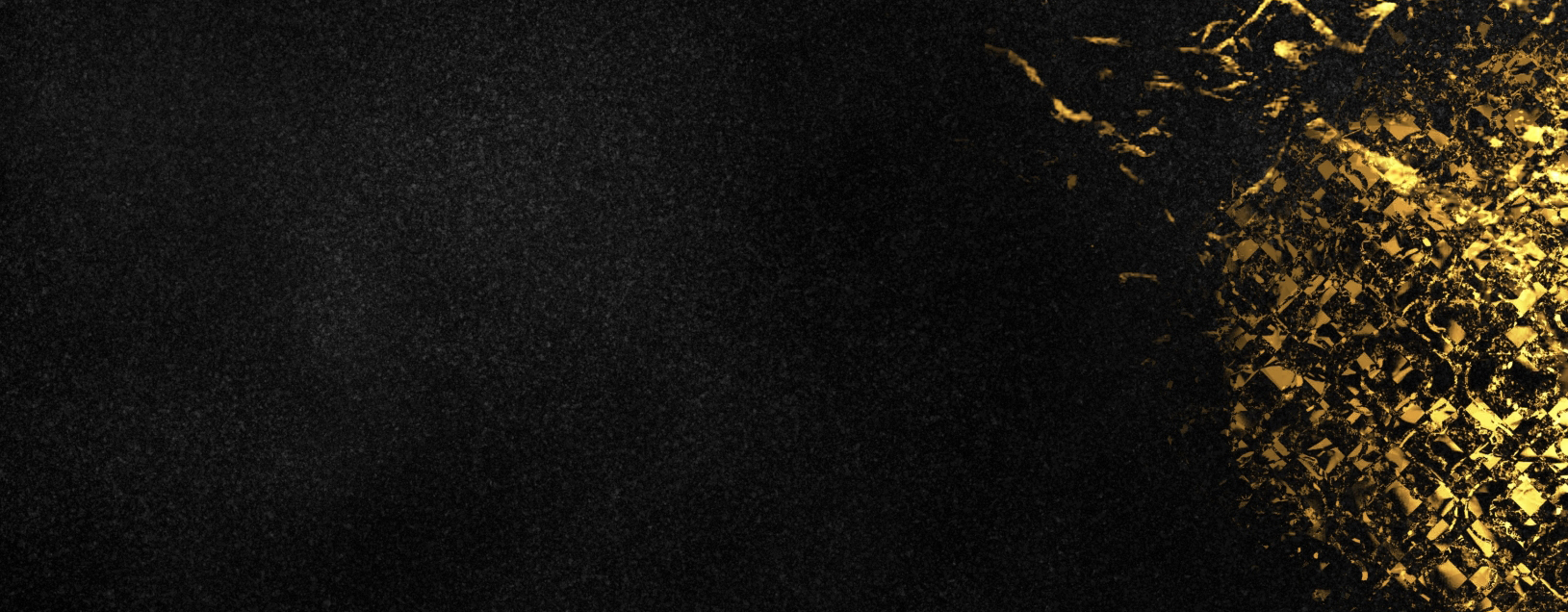
1902年 京都で生まれる。
1914年 京都市立陶磁器試験場付属伝習所轆轤科に入所。
1917年 卒業後、同試験場で助手として勤務する。
1921年 陶磁器試験場を辞め、富本憲吉に師事する。
1924年 清水新道石段下に窯を構え制作を始める。
1977年 「染付」で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
陶芸家の近藤豊は長男、近藤濶は次男、近藤高弘は孫にあたる。
染付とは酸化コバルトを原料とする絵の具を使います。代表的なものに呉須があり、素焼きした素地に絵や模様を描いて透明釉をかけて焼成します。一言でいえば白地に藍色の下絵が描かれた技法といえます。
近藤悠三は京都市立陶磁器試験場を卒業後、同試験場助手となり、この時期技手をつとめていた河井寛次郎・濱田庄司と出会い技術を磨きました。19歳の時、濱田庄司の紹介でイギリスから帰国して大和に窯を構えた富本憲吉の助手になっています。そこで素地や釉薬などの技法だけでなく、制作に対する心構えについても指導を受けています。
京都に戻った後、オリジナリティを追求すべく、浅野忠が設立した関西美術院でデッサンと西洋絵画を学び、河合卯之助からは陶芸を、津田青楓から書と図案を学んだといわれます。そこから確かな作陶技術と画才が融合した独自の作品が生まれます。
つけたてとぼかしを基調とした筆遣いによって濃淡を表し、ザクロや梅などをモチーフとして絵画的な表現をなした。さらに1960年以降は呉須染付に併用して赤絵や金彩の技法を用いるようになり、さらに独特の作風を確立しました。
染付技法は16世紀末に九州の有田地方に伝わり、京都で本格的に磁器の生産がされるようになったのは18 世紀後半である。その多くは「古染付」や「祥瑞」とよばれる中国製品の写しや、伝統的な技術やスタイルを中国に習ったものが中心であり、新しい独自の試みはほとんどなされなかった。
近藤悠三は、その染付技法を伝統的な枠組から新しい芸術表現へと昇華させました。
その染付は「近藤染付」とも呼ばれる。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。