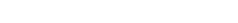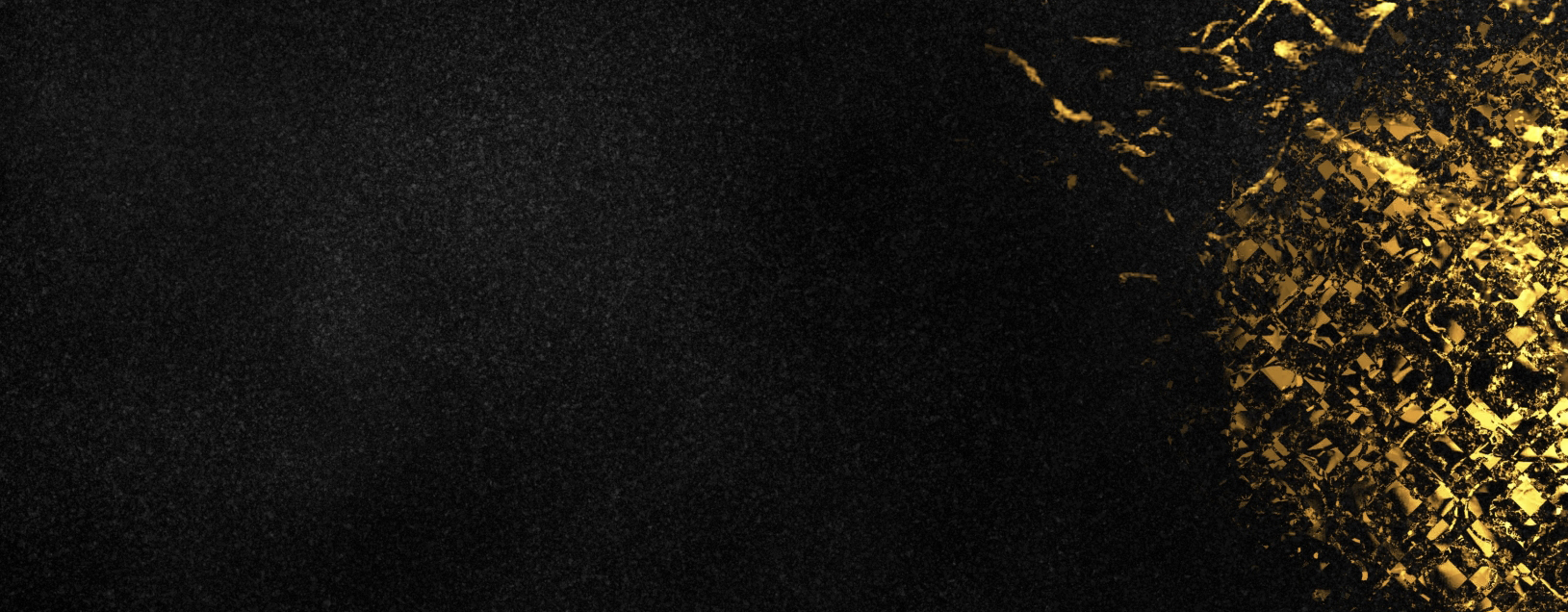
お知らせnews
2023.02.14
◇ 作家紹介 ◇ 三代 徳田八十吉
三代 徳田八十吉(とくだやそきち)
1933年 石川県に生まれる。
1954年 金沢美術工芸大学中退後、祖父初代・父二代に師事する。
1988年 三代目を襲名。
1997年 「彩釉磁器」で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
「彩釉磁器」とは本焼きした磁器に複数の釉薬を焼きつける技法です。
彩釉とは釉薬を用いて彩色を施すことであり、九谷焼や伊万里焼などの色絵磁器も彩釉の一種といえますが、色絵磁器が低温で色を焼きつけるのに対し、彩釉磁器は非常に高温で焼成することにより強い透明度や深み、豊かなグラデーションの表現が可能となります。
三代徳田八十吉は石川県の窯元の家系に生まれます。
祖父にあたる初代八十吉は古九谷様式の技法に秀でた名工で、吉田屋窯風の作風を得意とし、浅倉五十吉の師としても知られます。古九谷再現のための釉薬の研究と調合に取り組み、自身が開発した色釉を「深厚釉」と名付け代々継承しています。
父である二代八十吉は国立陶磁器試験所で富本憲吉の指導を受けます。色絵の洒脱さが特徴で従来の九谷様式を引き継ぎながらも、斬新な絵付けが魅力です。
三代徳田八十吉の作品は釉薬で色彩を調整した鮮やかな群青色に強い個性があります。白い磁胎に青・紫・緑・黄色を基調としてそれぞれの中間色を配置し、その結果、色と色をつなぐグラデーションが美しく、日本古来の九谷様式というより、現代の色彩豊かな抽象陶磁といった感じを受けます。代名詞となる「燿彩」に見られる自己の様式、すなわち特有の透明感のある色調と段階的な色彩の変化を確立します。
従来の九谷が「色絵とその意匠」に個性をあらわしているのに対し、三代八十吉の作品は九谷の色釉を用いながら「色」そのものを主軸にしています。従来の九谷焼を模範としながらも、花鳥をはじめとする描写的な上絵付による色絵の世界を超えて、色の追求という点で造形も色彩も現代的な作風であり、九谷焼の色彩の無限の可能性を広げました。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。