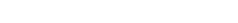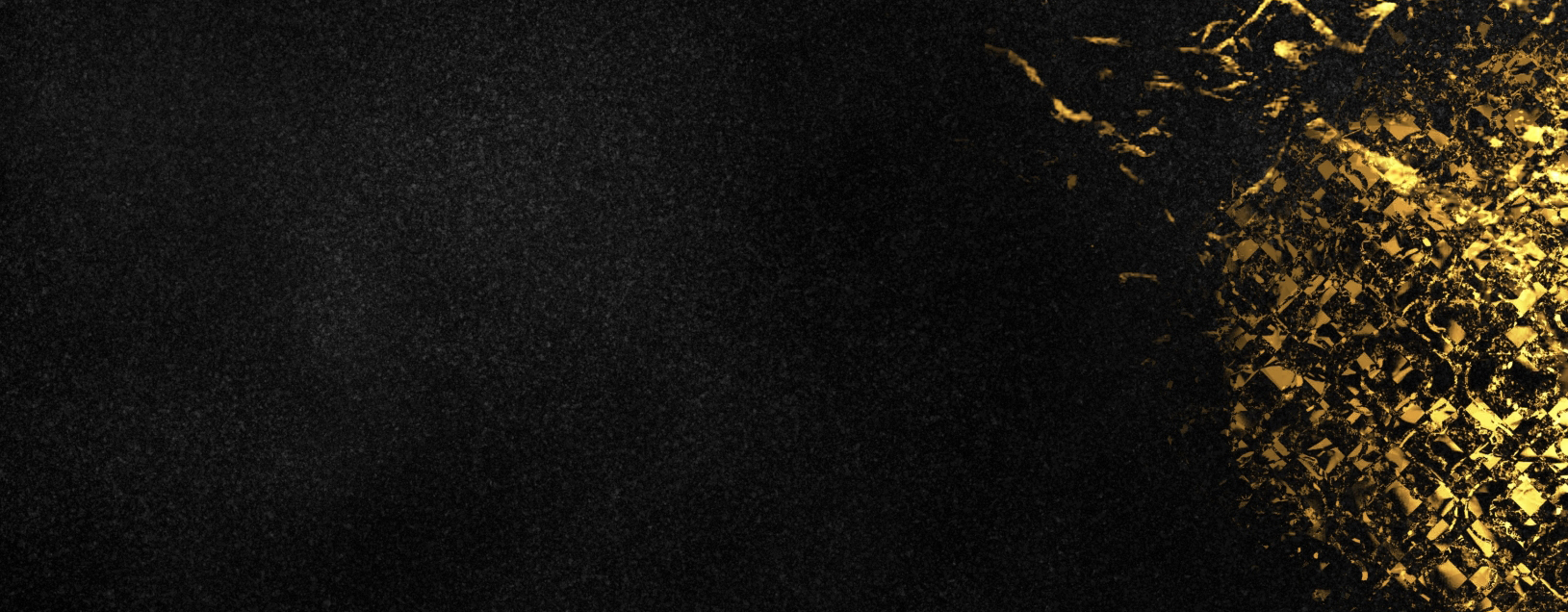
お知らせnews
2023.02.16
◇ 作家紹介 ◇ 三代 山田常山
三代 山田常山(やまだじょうざん)
1924年 愛知県に生まれる。
1941年 愛知県立常滑工業学校窯業科を卒業。
在学中より 祖父・初代 山田常山に師事。
1946年 父 二代 山田常山に師事。
1961年 三代 山田常山を襲名する。
1998年 「常滑焼 (急須)」で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
常滑は平安時代の後期から現代まで続く窯業地です。知多半島の丘陵に築かれた古窯では、早くから大型の壷や甓が焼かれ、全国に供給されていました。
中世から続く日本を代表する6つの窯場「日本六古窯 」。常滑焼はこの日本六古窯のひとつで、その中でも当時最大規模の産地といわれています。
三代 山田常山は、祖父・初代常山、父・二代常山と二代続く急須づくりを専門とする陶家の長男として生まれる。祖父は妥協を許さない厳しさと精緻な作風で名工と謳われ、父もその技を継承した名手として名を馳せた陶工である。その二人に少年のころから基礎的な陶技を学び、中学に入るころには急須づくりを始める。
三代常山の急須は、地元で産出される粘りの強い朱泥土を用い、本体、注口、把手、蓋のすべてを、轆轤を使って成形し、それらを組み立ててつくり上げる。朱泥土をベースとした、朱泥、紫泥、黒色の烏泥に加え、象牙色の白泥、古常滑を祖とする自然釉や、土そのものの風合いを生かした焼き締めによる南蛮、備前のように火襷の走った急須など多彩な作品がある。形のバリエーションも広く、煎茶具として用いる伝統的なものから、北欧のデザインに触発されたモダンなものまで、100種類以上を優に超え無限である。それらは、すべてに卓越した轆轤技術があってこそ生み出されるのである。
また三代常山は、早くから後進の指導にも積極的で、「常滑『手造り急須』の会」が設立されると会長に就任し、30年に亘り模範的な活動を通して技術の継承に尽力し、多くの後進を育て上げるとともに、急須の発展に貢献しました。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。