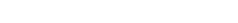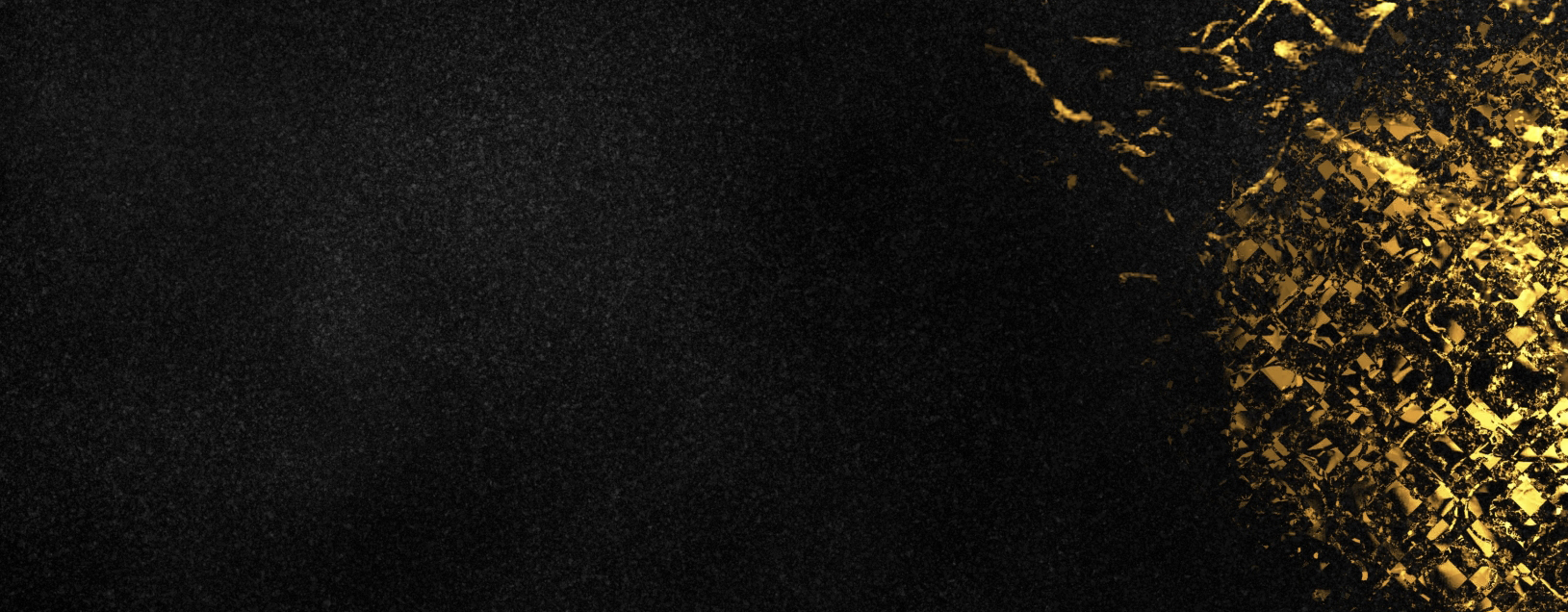
お知らせnews
2023.02.17
◇ 作家紹介 ◇ 中里無庵
中里無庵(なかざとむあん)
1895年 佐賀県に生まれる。
1927年 十二代中里太郎右衛門を襲名する。
1969年 京都大徳寺にて得度し、号無庵を受ける。
1976年 「唐津焼」の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
唐津焼の起源は諸説ありますが、室町時代末から桃山時代にかけて、岸岳城城主波多氏の領地で焼かれたことが始まりとされています。その後、豊臣秀吉による朝鮮出兵の際に、朝鮮陶工を連れて帰り、その陶工たちが各地で窯場をつくり焼き始めたことで、唐津焼の生産量は拡大していきます。登り窯や、蹴ロクロ、釉薬法など、朝鮮渡来の技術の導入によって作風や種類も豊かになり、全国に流通し、西日本では焼物のことを「からつもの」と呼ぶほどまでに有名になりました。
また、古くから茶の世界では、「一井戸、二萩、三唐津」と言われ、茶の湯の名品として多くの茶人に愛され、江戸時代には唐津藩の御用窯として発展しました。明治維新を迎えると藩の庇護を失った唐津焼は衰退しますが、中里無庵が古唐津の技法を復活させ、勢いを取り戻しました。
中里無庵は、江戸時代から続く陶家で藩の御用窯の伝統を持つ「御茶盌窯」窯元11代中里太郎右衛門の次男として生まれる。佐賀県立有田工業学校を卒業後、父の元で学びながら家業に就きます。
1929年からは佐賀・長崎両県下の古唐津窯跡発掘調査に着手し、唐津焼の主流であった献上唐津風の作調に疑問を感じていた無庵は、出土した素朴な味わいの古唐津に魅了され、古唐津陶技を復興するべく、出土した陶片や資料などを基にその技術の分析・研究に努めます。
再現に成功した古唐津製法に「叩き」という技法があります。輪積みした粘土の内側に当て木をして、外側から叩いて形を整える技法です。そして、自らの作陶にも研究の成果を生かし、独自の「叩き技法」を軸にした作風を築き、失われた唐津の技法と作風を現代に甦らせました。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。