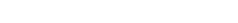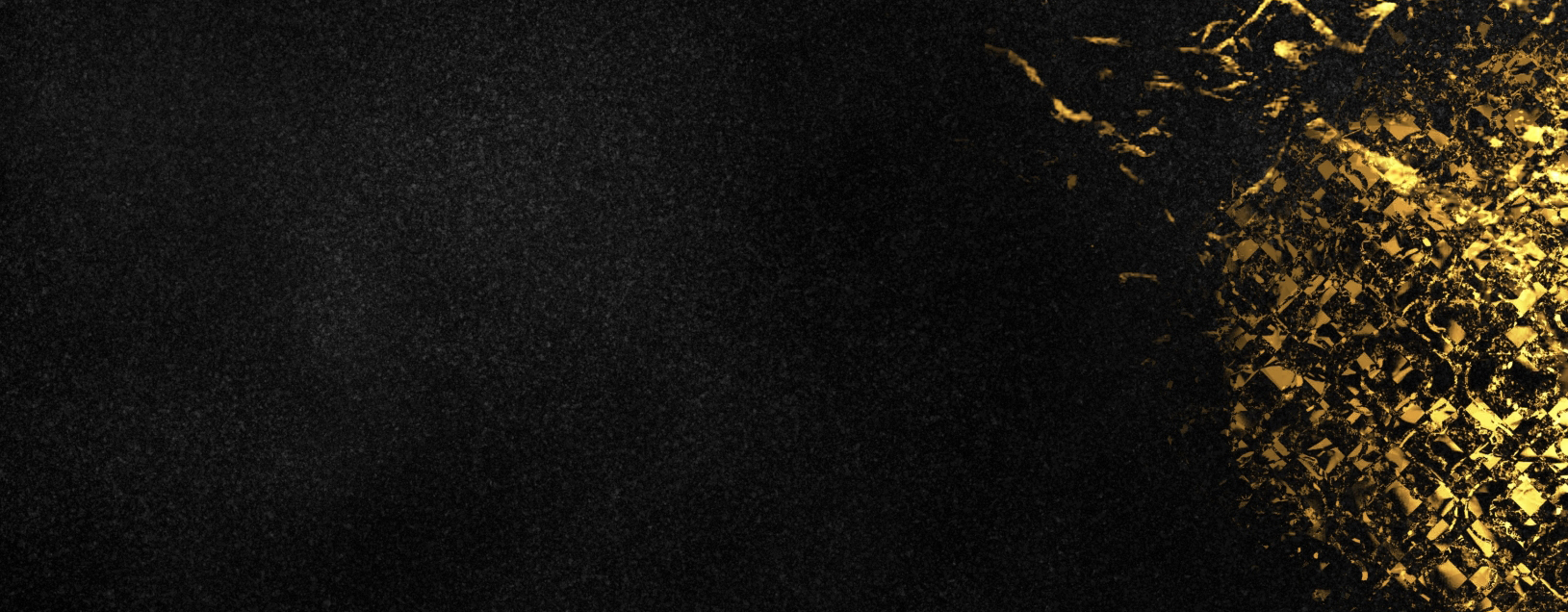
お知らせnews
2023.03.02
◇ 作家紹介 ◇ 大場松魚
大場松魚(おおばしょうぎょ)
1916年 石川県に生まれる。
1943年 金沢市県外派遣実業練習生として松田権六に師事する。
1964年 国宝中尊寺金色堂保存修理の漆芸技術者として従事する。
1982年 「蒔絵」の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
大場松魚は石川県金沢市に生まれます。 工業学校卒業後、塗師であった父の大場宗秀もとで家業の髹漆を学ぶ。その後、金沢出身の漆芸家で東京美術学校教授の松田権六の内弟子となり師事する。2年間の修業を積み金沢に帰り、本格的な作家活動に入る。
伊勢神宮式年遷宮の御神宝の制作や国宝である中尊寺金色堂の保存修理に従事し、古典技法に対する造詣を深めつつ、のちに大場松魚の代名詞となる蒔絵の分野の一技法であった「平文(ひょうもん)」による意匠表現を探求して独自の道を開いた。
平文技法とは、奈良時代に栄えその後ほとんど使われなくなっていた技法であり、金や銀の板を文様の形に切り、器面に貼り付けて、その上に漆を塗り重ね、研ぎ出すか金属板上の漆の膜を削り取って文様をあらわす技法である。
大場松魚の平文は、蒔絵粉に比して強い存在感を示す金属板の効果を意匠に生かす一方、筆勢を思わせるほど繊細な線による表現も自在に取り入れ、これに蒔絵、螺鈿、卵殻、変り塗などの各種技法を組み合わせて気品ある作風を築きました。
また多くの弟子を自宅工房に受け入れ、研修・教育機関においても、輪島市漆芸技術研修所の講師や、金沢美術工芸大学の教授として学生を指導し、後継者育成に尽力した功績は大きい。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。