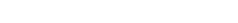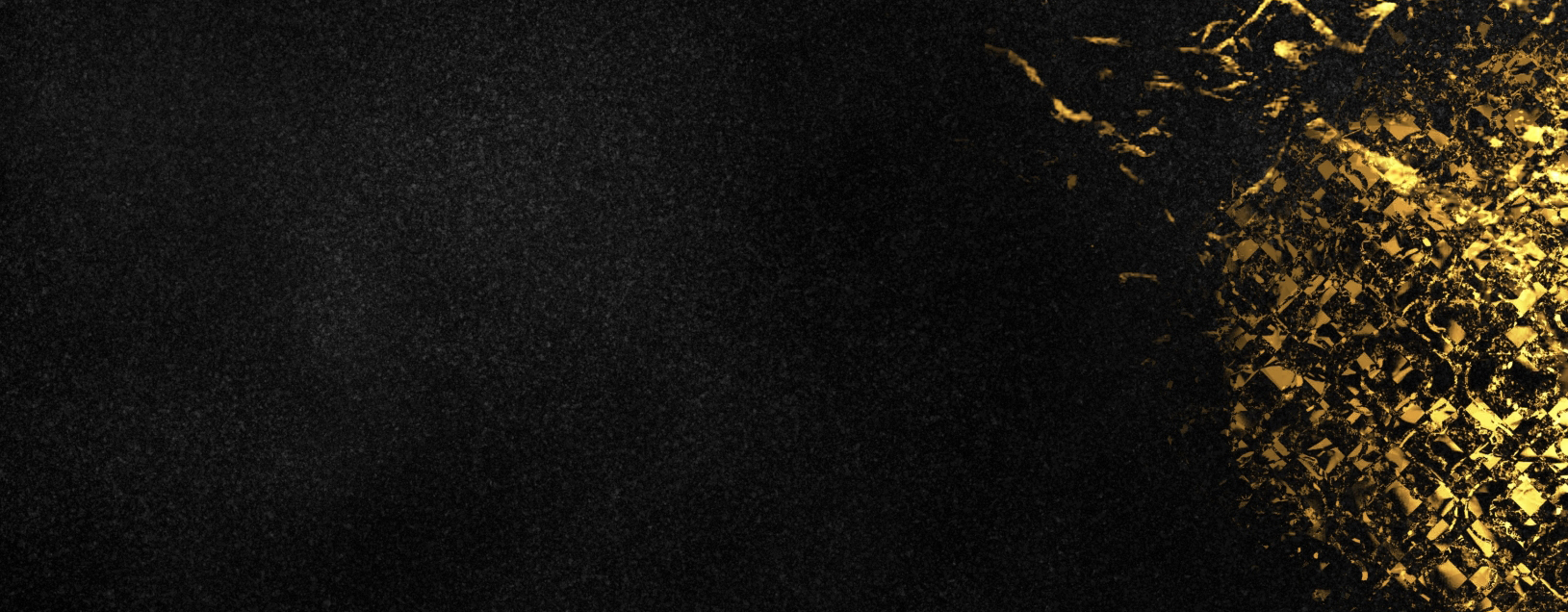
お知らせnews
2023.03.26
◇ 作家紹介 ◇ 魚住為楽
魚住為楽(うおずみいらく)
初代魚住為楽
1886年 石川県に生まれる。
1955年 「銅鑼」の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
初代魚住為楽は石川県小松市に生まれます。本名は安太郎。大阪久保田鉄工所に入所し金工業を学び、仏具師の山口徳蔵に弟子入りし、仏具製作修業のかたわら鈴の鋳造について研究します。その後、金沢にて銅羅について独学で研究をはじめます。また正木直彦、香取秀真について砂張鋳造を研究する。
砂張(さはり)は銅に錫、鉛を加えた合金である。砂張は硬いうえにもろく、また鋳造には鬆(す)ができやすく、金工材料のなかでも取扱いがむずかしいが、為楽はことにこの砂張を用いた鋳造を得意とし、銅羅をはじめ花入れ、建水などの茶道具に優れた作品を残しました。
魚住為楽の銅鑼づくりは他の工芸品と違い基本的に使用目的を重視し、卓越した音感により音色、余韻を研究し、砂張を用いて音響に重厚感を与える。また造形においても合金、鋳造、熱処理など各技法を熟練し高い技術力を示しました。
三代魚住為楽
1937年 石川県に生まれる。
2002年 3代魚住為楽を襲名する。
2002年 「銅鑼」の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
三代魚住為楽は石川県金沢市に生まれる。本名は安彦。二代目だった父が戦死し、祖父の初代魚住為楽より高校生の頃から砂張の加工技術を学ぶ。名工と言われた初代の技術を継承し、鋳型づくりから仕上げまで一貫して行い、様々な名品を生み出します。深みのある鈍い輝きと、えもいわれぬ余韻を残すその音色は、「砂張」という独特の素材と、長年にわたり磨いてきた技の賜物である。
銅鑼づくりは、数々の複雑な工程があり、気温の関係で作業ができるのは春と夏だけとなり、1年をかけても出来上がる作品はほんのわずかで、おのずと大変希少なものになります。銅鑼づくり以外の季節は、砂張を使った茶道具の水差しや花生けのほか、風鈴なども制作し、伝統的な技法を用いながら、象嵌などで繊細な装飾をほどこし、どこかモダンな印象を受ける格調高い作品に仕上げています。
初代魚住為楽は「音は宇宙」と表現し、三代魚住為楽は音を「命」と捉えて日々向き合い、その技術は「魚住の砂張」と呼ばれ、高い評価を受けています。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。