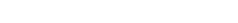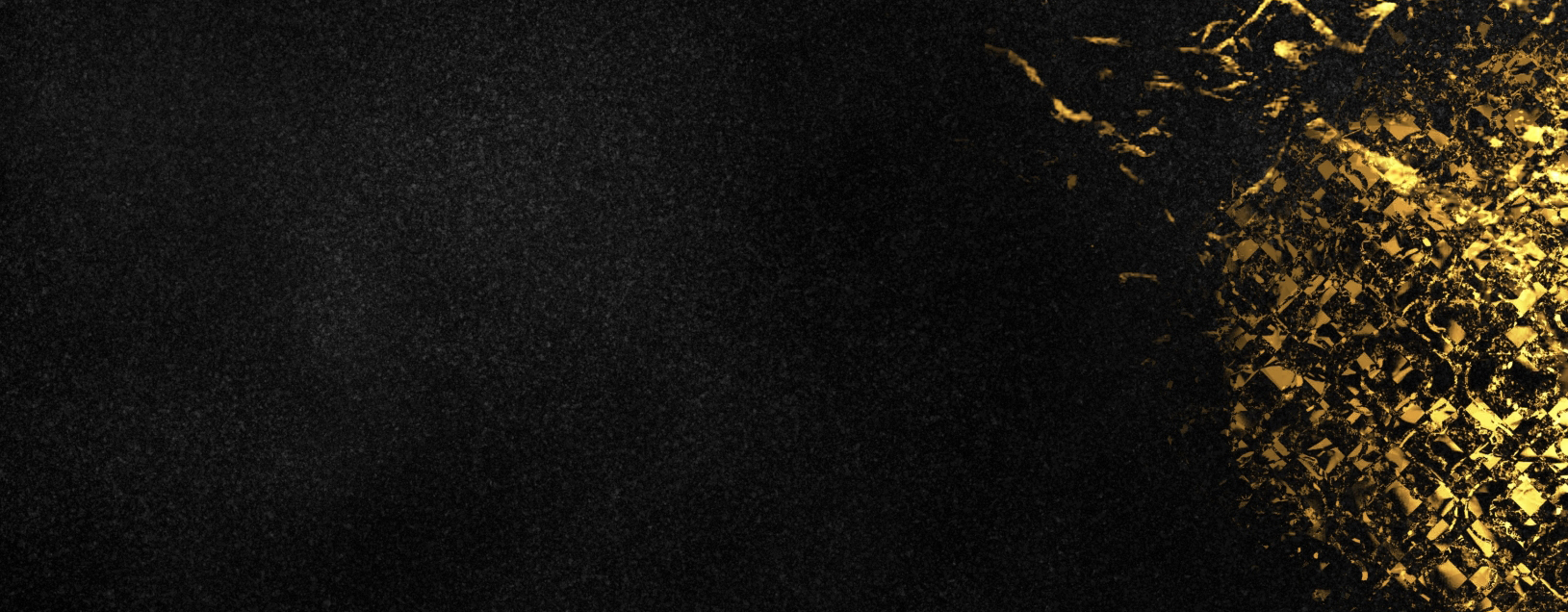
お知らせnews
2023.03.31
◇ 作家紹介 ◇ 長野垤志
長野垤志(ながのてつし)
1900年 愛知県に生まれる。
1923年 山本安曇に師事する。
1928年 香取秀眞に師事する。
1963年 「茶の湯釜」の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
長野垤志は名古屋市東区に生まれ、本名は松蔵。はじめ洋画家を志し上京しました。早稲田大学附属早稲田工手学校、本郷洋画研究所で学び、関東大震災により同所が焼失しため、これを転機に鋳金家に転じます。山本安曇に師事し、のち香取秀真に就き作品指導のほか古美術研究の指導を受けます。その後、名古屋の釜師・伊藤一正と知り合い茶の湯釜の研究に取り組むようになります。
かつて桃山時代は釜一個、屋敷一軒と言われ、権力者でなければ決して持つことが出来なかった茶の湯釜。江戸中期になると庶民の中でもお茶が普及されていきます。江戸後期になると釜作りは海外から輸入された鉄鋼石を原料とする洋銑(ようくず)が主流になっていきます。
長野垤志は「作るなら10年20年で朽ちる洋銑の釜ではなく、古(いにしえ)の茶の湯釜のように、膚や模様が美しく写る和銑(わずく・砂鉄を集めて、たたらで精錬した鉄)で」と考え作ってみますが、一度途絶えた技術を取り戻すことは難しく、和銑の釜はそう簡単には作れませんでした。そこから和銑の魅力に益々惹きつけられ、古の茶の湯釜の研究に生涯を捧げます。
長野垤志は昭和を代表する釜師として活躍し、砂鉄による和銑釜の鋳造法を復原するなど、日本古来の製造技術を生かして高い芸術性と格調のある現代茶の湯釜を生み出しました。また釜に関する学問的研究にも造詣が深く、『芦屋の釜』『天命の釜』『茶の湯の見方』などの著書があります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。