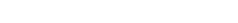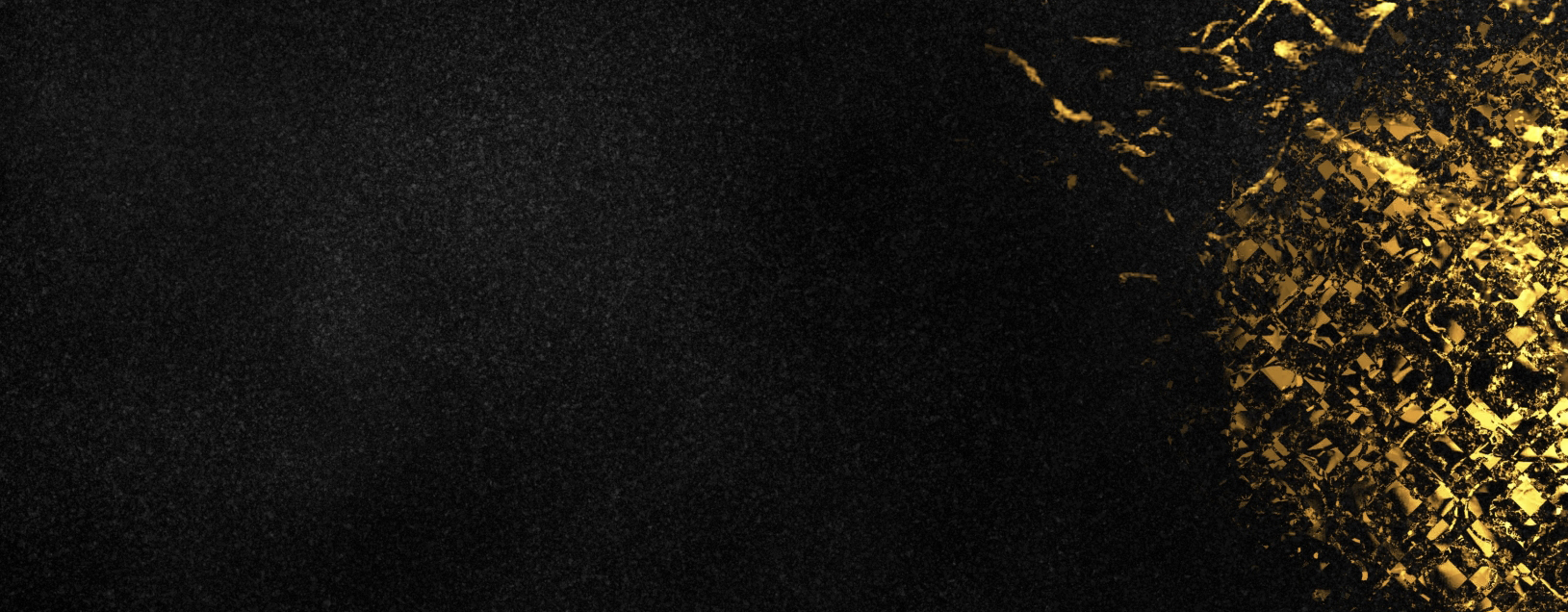
お知らせnews
2023.04.13
◇ 作家紹介 ◇ 大澤光民
大澤光民(おおざわこうみん)
1941年 富山県にに生まれる。
1958年 富山県職業補導所銅器科を卒業する。越井銅器製作所に就業。
1969年 大澤美術鋳造所を設立する。
1975年 光民と号する。
1977年 通産省の「伝統工芸士(銅器焼型鋳造部門)」に認定される。
2004年 卓越技能賞「現代の名工」として表彰される。
2005年 「鋳金」の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
大澤光民は富山県高岡市に生まれ、本名は幸勝(ゆきまさ)。中学卒業後に富山県立職業補導所で伝統的な鋳金技法を学び、17歳で越井銅器製作所に就業します。27歳の時に高岡市特産産業技術者養成スクールを受講し、ものをつくる力と感性の大切さを学びます。その後も人間国宝の香取正彦をはじめ多くの名工たちに学び、歴史的な器物に関する知識や技術を深めていきます。
高岡銅器の伝統的な「焼型鋳造」技法に習熟し、独自に考案した「鋳ぐるみ」技法によって鋳金の世界に新たな加飾表現を生み出すなど、高岡の伝統工芸全体を牽引してきました。
「焼型鋳造」とは、真土(まね)と呼ばれる土で鋳型を作り、約900℃で焼いたのち、約400℃に冷ましてから溶解した金属を流し込む技法であり、小さくて複雑な置物から大きな銅像まで製作する技法です。
「鋳ぐるみ」技法とは鋳型に予めステンレス線や銅線などの金属線を釘で固定し、溶けた金属を注ぎ込む。焼型鋳造によって鋳型を焼き上げるときに、打ち付けた金属線が動いたり膨張したり金属の種類によって地金に溶け込んだりするため、象嵌とは異なる偶然の味わいをもつ文様を創り出すことができます。
大澤光民は「銅線の赤は太陽、ステンレスの白は水をイメージしています。朝日や夕日の美しい景観、太陽と水が生み出す生命の不思議な造形にいつも感心させられます。同じ畑、土で育っても花や野菜の色や形はさまざま。そんな自然の妙や素晴らしさ、人間愛、温もりなどを伝えられれば」と語る。
その作風は、独創的な「鋳ぐるみ」技法によってもたらされる、偶然性でできた模様が奏でる有機的な温かさと、現代的で洗練された美しさの共存が何よりの特徴で、宇宙や生命の尊さなど、壮大で人間愛あふれる普遍的なメッセージが込められた多彩な作品は高く評価されています。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。