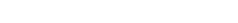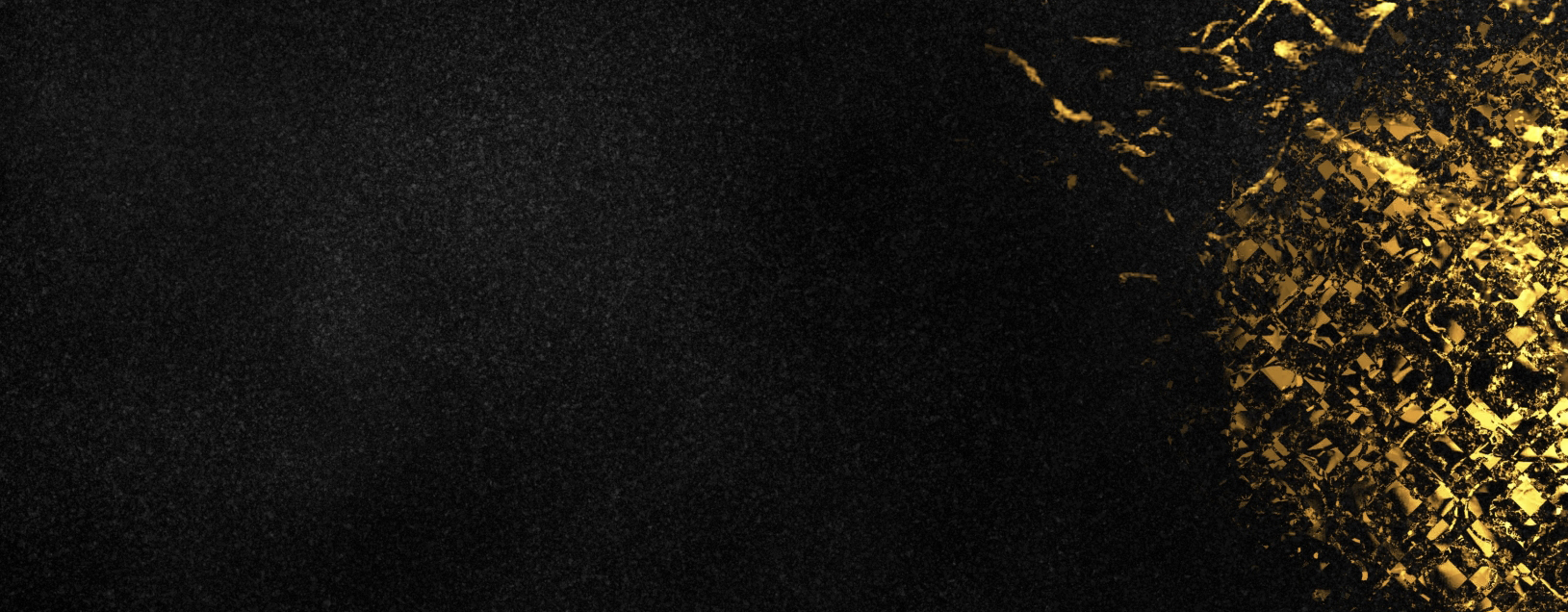
お知らせnews
2023.05.11
◇ 作家紹介 ◇ 勝城蒼鳳
勝城蒼鳳(かつしろそうほう)
1934年 栃木県に生まれる。
1949年 竹細工師・菊地義伊に入門する。
1965年 竹工芸家・八木沢蒼玕(啓造)に師事する。
1968年 竹工芸家・斉藤文石の指導を受ける。「蒼鳳」の号を用いる。
2005年 「竹工芸」の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
勝城蒼鳳は栃木県那須塩原市に生まれる。本名は一二(いちじ)。父もかご職人であったが、より厳しい道をと、15歳で主に実用品である農作業用のかごをつくる竹細工師・菊地義伊もとで住み込み修業に出される。6年間の修行を終え、実家に戻り独立する。
しかしプラスチック製品や段ボールの普及によって仕事が激減していく。そこで竹割りの技術が生かせるということで、大田原で竹工芸の創作と後進の育成に力を注いでいた八木澤蒼玕(啓造)の主宰する八木澤竹工房で仕事をはじめます。勝城はここで創作の喜びに目覚める。非凡な才能はすぐに開花し、2年間勤めた後、「蒼鳳」という雅号をもらい、竹工芸の道に進むことを決意して独立を果たす。
その創作意欲はとどまるところを知らず、昭和43年の第15回日本伝統工芸展に出品以来、50年近く出品し続けている。しかも、毎回、表現技法をがらりと変えているという。
独立後、作品で行き詰まったときには、日本を代表する竹工芸家・飯塚琅玕斎(いいづかろうかんさい)の高弟であった斎藤文石(さいとうぶんせき)の指導を受ける。県の竹工芸指導員でもあり、すべてを惜しみなく教えてくれる人であったという。
勝城蒼鳳は竹の選定に始まり素材の調整、編組、染色・拭漆仕上げ等にわたる幅広い竹工芸技法を高度に体得しており、丹念な編組や捻り、膨らみの量感と仕上げで独創的な作品を作り出しています。創作のモチーフは毎日のように目にする自然の情景であり、土の匂いや季節の移ろい、大地から吸い取った生命力が込められた作品の数々は高く評価されています。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。