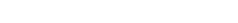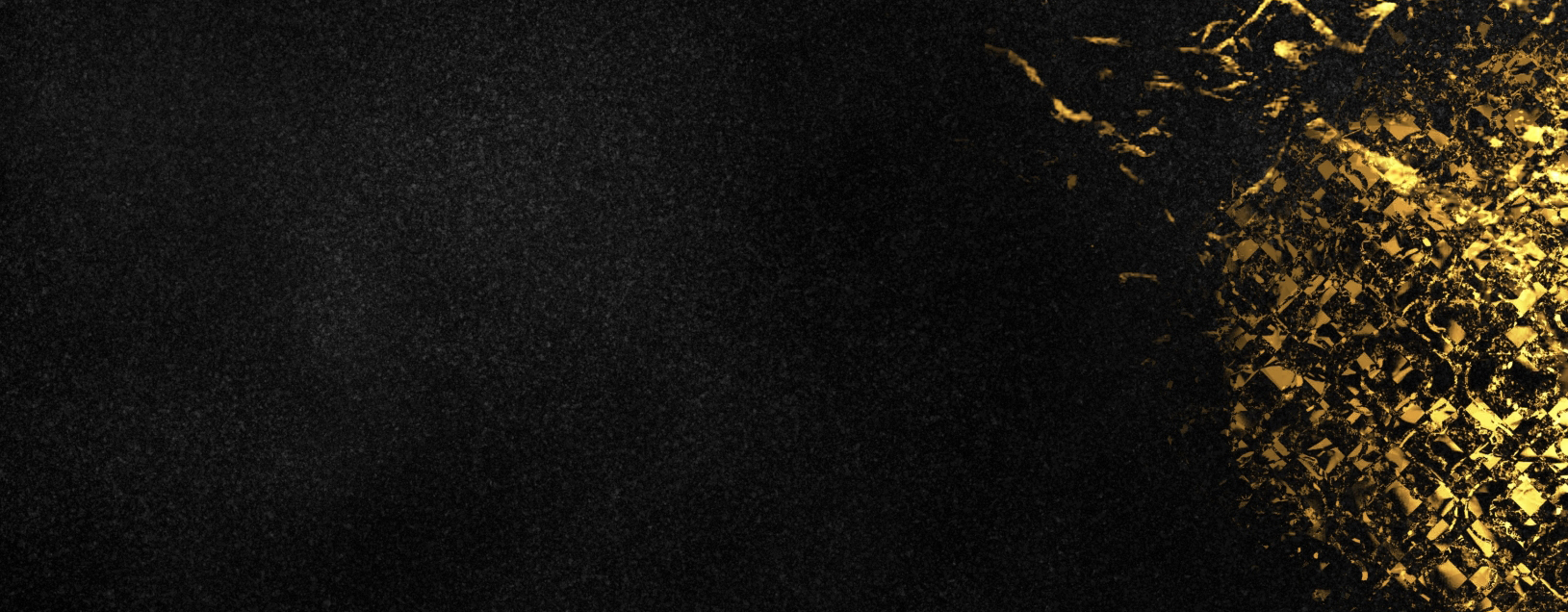
お知らせnews
2023.02.13
◇ 作家紹介 ◇ 三輪休雪
三輪休雪(みわきゅうせつ)
三輪窯は山口県萩市にて、江戸時代寛文年間に起こったと言われ、代々坂高麗左衛門の坂窯と共に萩藩の御用窯を務めていた由緒ある窯元である。
十代休雪(休和)・十一代休雪(壽雪)は、国の重要無形文化財保持者(人間国宝)に指定されています。十代休雪によって開発された藁灰の釉薬を十一代休雪が大成させた白い釉薬は「休雪白」と呼ばれ有名です。
現当主 十三代 三輪休雪は、三輪家の伝統を継承しながらも、独自の世界観を打ち立て前衛的な創作を行っています。
十代 三輪休雪 (休和)
1895年 9代三輪雪堂の次男として生まれる。
幼少期より祖父・8代三輪雪山から陶工としての薫陶を受ける。
1927年に10代三輪休雪を襲名。
1941年に川喜田半泥子が三輪窯へ来遊した事を機に、翌年に三重県津市の半泥子宅に招かれ、川喜田半泥子、荒川豊蔵、金重陶陽と「からひね会」を結成。
茶陶の本格的な近代化はここに始まり、桃山陶磁の研究も一層進展しました。
1970年に「萩焼」で重要無形文化財保持者(人間国宝)に 認定。
萩焼の源流である高麗茶碗の研究に打ち込みながら桃山茶陶の研究を重ね、温雅な趣に富んだ休和様式を確立させました。萩焼の特色である白釉に関して独特の技法を編み出し、「休雪白」とよばれるようになる。
陶芸の中では比較的歴史の新しい萩焼を、瀬戸焼や備前焼等に代表される古窯と同等レベルにまで引き上げることに貢献しました。
十一代 三輪休雪 (壽雪)
1910年 9代三輪雪堂の三男として生まれる。
兄の10代三輪休和と川喜多半泥子に師事する。
1967年、11代三輪休雪を襲名。
1983年に「萩焼」で重要無形文化財保持者(人間国宝)に 認定。
萩焼の伝統を受け継ぎながらも斬新で卓抜した感覚を駆使し、前例の無い日本伝統工芸史上初の兄弟人間国宝となる快挙を成し遂げました。
白釉と大胆な造形で独特の休雪様式を確立して、その技法・伝統を現代に活かしています。
兄と大成した「休雪白」を始めとし、休雪碗ともいうべき「鬼萩」、「割高台」は茶陶という概念を超え、一個のオブジェといえる極致にあります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。