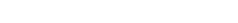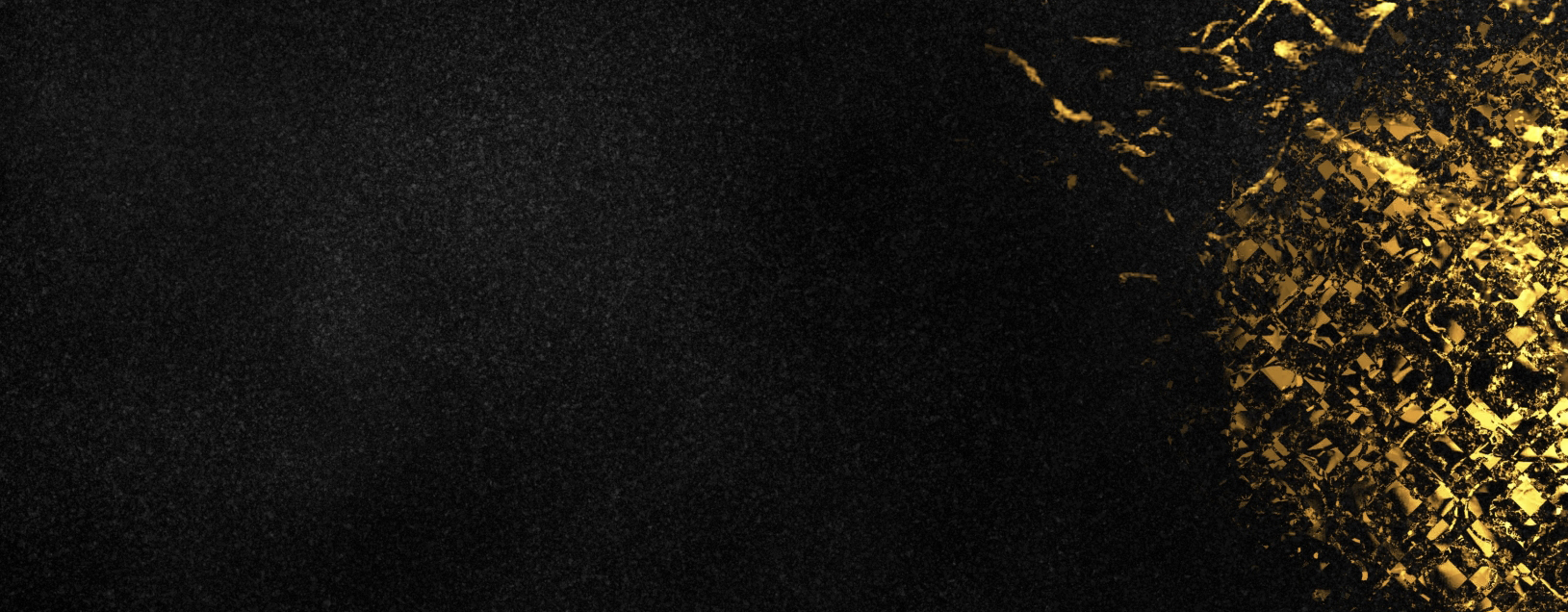
お知らせnews
2023.02.16
◇ 作家紹介 ◇ 島岡達三
島岡達三(しまおかたつぞう)
1919年 東京都に生まれる。
1939年 東京工業大学窯業学科に入学。
1940年 益子に濱田庄司を訪れ、卒業後の入門を許される。
1946年 戦後、すぐに濱田庄司門下となる。
1950年 栃木県窯業指導所に勤務。
1953年 益子に住居と窯を設ける。
1996年 「民藝陶器・縄文象嵌」にて重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
縄文象嵌とは作品に縄目を施して色の違う土をはめ込む(象嵌する)技法です。
島岡達三によって考案されました。
大学在学中に日本民藝館を訪れ、濱田庄司や河井寛次郎の作品に触れ民芸の美に目覚め、また柳宗悦の民芸論に触れ鼓舞され、「民芸陶工の道」へと進むことを決意する。
濱田庄司に学生の時分から益子に直接出向いて弟子入りを志願し認められ、在学中から濱田の元で体験入門をし、大学一年目には轆轤修行をし、二年目には「小田部製陶所」で修行しながら、濱田の勧めにより西日本各地の民窯を見聞してまわる。そして太平洋戦争の影響を受け、大学を繰り上げ卒業し徴兵検査を受け、軍隊に入隊。終戦後、1946年に復員し、ようやく濱田への正式な弟子入りを果たした。
三年間の修行の後、濱田の紹介により栃木県立窯業指導所へ技師として入所し、粘土や釉薬を徹底的に試験研究した。その一方で、濱田に付いて全国各地の博物館や大学へ赴き、古代土器の標本複製の仕事を手伝い知識を深めます。
朝鮮李朝の古典的な彫三島の技法からも影響を受け、三代続く組紐師である父に組んで貰った紐を使い縄文を施し、更に象嵌を成していく「縄文象嵌」の技法を修得していきます。この技法に地元の素材を使った柿釉や黒釉などの六種の釉薬と、独自に工夫した釉薬を組み合わせ多彩な表現を展開していく。
生家での組紐から体得した技を縄目文様であらわし、象嵌と組み合わせる事で独自の境地を見出し、益子における一つの作風を確立しました。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。