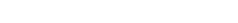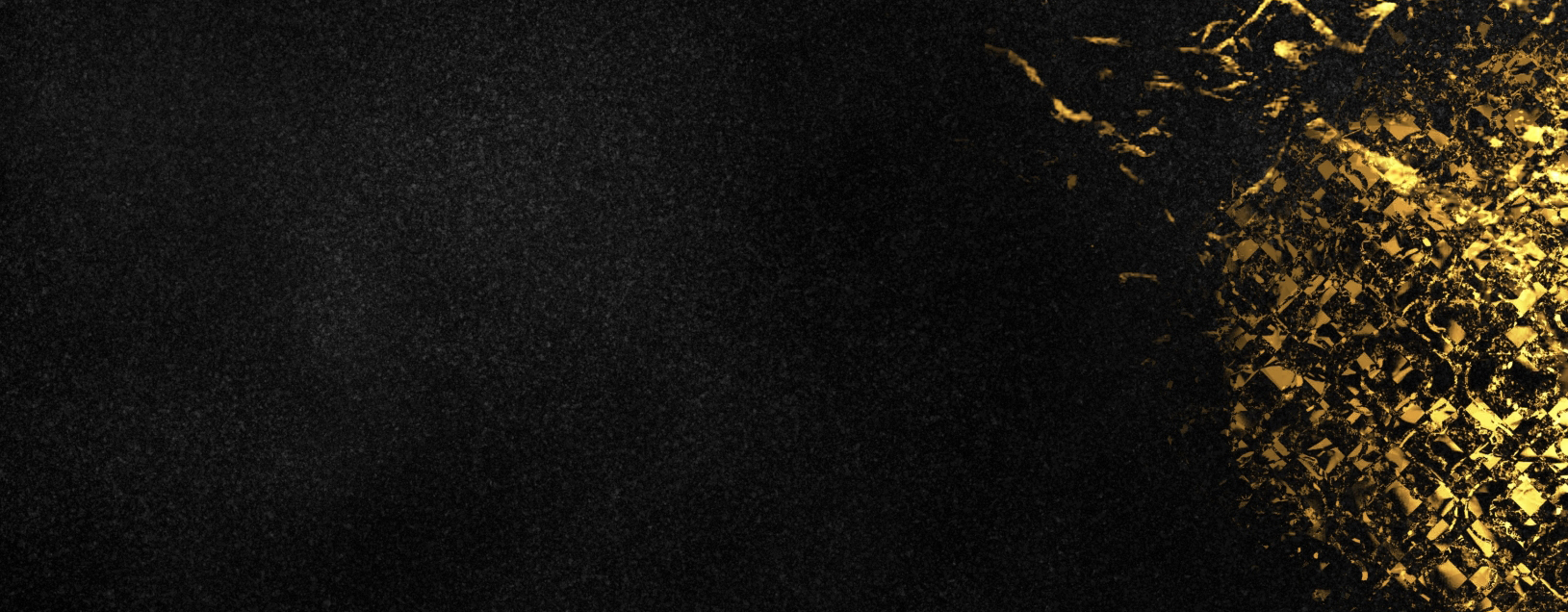
お知らせnews
2023.02.17
◇ 作家紹介 ◇ 加藤卓男
加藤卓男(かとうたくお)
1917年 岐阜県に生まれる。
1935年 岐阜県多治見工業学校を卒業。
1961年 フィンランド工芸美術学校に留学する。
1973年 イラン国立パーラヴィ大学付属アジア研究所留学およびペルシャ古陶発掘に参加。
1980年 宮内庁より正倉院三彩の復元制作を委嘱される。
1995年 「三彩」で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
三彩とは2種類の釉薬で加彩した陶磁器のことです。
白い胎土に緑・飴色の釉薬をかけた奈良三彩などがあり、中国では漢や北斉の三彩・唐代の唐三彩、明代の華南三彩なども有名です。三彩の起源は中国や中近東で1~2世紀ごろには作られています。。
加藤卓男は江戸時代から続く美濃焼窯元の五代目加藤幸兵衛の長男として生まれます。父である五代加藤幸兵衛は金襴手や青磁の名工として知られます。
卓男は18歳で京都の商工省陶磁器試験所に入所して陶技を磨きました。同試験所終業後、帰郷し家業の幸兵衛窯に勤務します。その後は戦争によって作陶を一時離れ、配属先の広島で被爆したためおよそ10年におよぶ療養生活を余儀なくされます。
1961年には陶磁器意匠と技術の交換のため、フィンランド工芸美術学校に留学する。この間、休暇を利用して中東各地の陶器の産地を訪れ、そこで古代ペルシア陶器に触れ古陶の美に愛着と魅力を感じる。
帰国後は本格的にペルシア陶、なかでもラスター彩の研究を志すようになった。そして、20年にわたる試練の時を経て、この壮大な試みを実現させ、ラスター彩復元の手がかりを解明し、その成果は息子の七代加藤幸兵衛によって引き継がれています。
ラスター彩とともに同じペルシア系統の青釉にも取り組み、独創的なフォルムと鮮やかな青色が融合した作品を制作した。そのほか三彩・志野・織部・染付・天目・青磁・赤絵などじつに多様な作陶をしています。
1980年には宮内庁より正倉院三彩の「三彩鼓胴」と「二彩鉢」の復元制作を依頼され、約7年間におよぶ研究と100回を超える試作を経て復元に成功する。この経験と技術を生かし、正倉院三彩とペルシア三彩を取り入れた独自の三彩陶を発表していきます。
ペルシア陶に魅せられ、研究のため訪れた中東の古窯址発掘現場で、織部に似た陶片を発見して以来、卓男はペルシアから日本へと広がる壮大なやきものの技術交流と発展史へと興味を広げた。そして、古代のペルシア陶の技法を解明、再現することにとどまらず、作家として、古陶磁研究を自己の表現の手段として昇華させ、誰もなしえなかった古代ペルシア陶と日本陶の融合を成し遂げました。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。