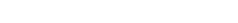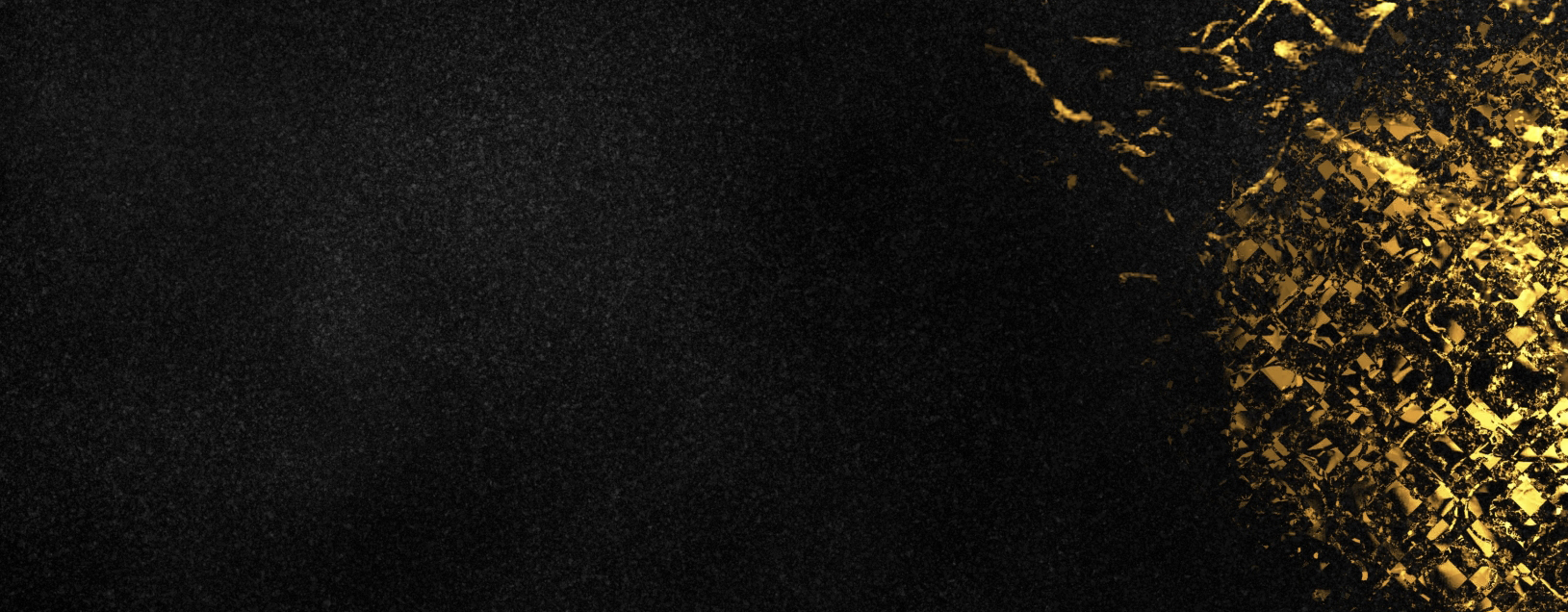
お知らせnews
2023.02.22
◇ 作家紹介 ◇ 今泉今右衛門
今泉今右衛門(いまいずみいまえもん)
1610年代に日本で初めての磁器が有田で焼かれました。その後1640年代に中国より赤絵(色絵)の技法が伝わり、その頃より初代今右衛門も赤絵付の仕事をしたと思われます。
江戸期には鍋島藩の御用赤絵師として指名され、特に赤絵の秘法が他藩へ洩れるのを防ぐため、藩は家督相続法をつくり、一子相伝の秘法として保護をしました。
明治になり藩の保護を失った後、十代今右衛門は従来の分業体制にのっとった上絵専業の家業から、素地づくり、本焼、上絵にいたるまでの一貫した制作に乗り出し、現在の今右衛門陶房の基礎を築きます。そして十代・十一代・十二代と三代かけて江戸期色鍋島の復興に成功し、十二代今右衛門の時代に「色鍋島」が無形文化財の指定を受け、1971年には”十二代を代表とする色鍋島技術保存会”が国の重要無形文化財保持団体の認定を受けました。
十三代今右衛門は、その造りだす技術は江戸期から伝わる手仕事であるが、色鍋島の世界に芸術性を加え、現代の色鍋島として吹墨・薄墨・緑地の技法を確立しました。
コバルトの染付の絵具を吹きつける「吹墨」の技法を用いて濃淡に富む地文の表現を実現し、さらに貴金属を含んだ黒色の顔料を、吹墨と同様の技法で地文に用いる「薄墨」の技法を創案して、複雑な色彩効果をもつ新たな色絵の表現を確立、そして中国・明代の緑地金彩にヒントを得て、緑の上絵具を地色として塗りこめる技法も好んで用い、白地や淡色地の多い従来の色鍋島に、新しい作風をもたらしました。
1989年に「色絵磁器」で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されます。
十四代今右衛門は鍋島の代々の仕事を継承しながらも、江戸期からある染付の中に白抜きの文様を作るときに用いる「墨はじき」と呼ばれる技法に着目する。
墨はじきによって描かれた個所は、染付の線描きされた個所と比べるとやさしい控えめな印象を与える。そのため主文様の背景に使われることが多かった。十四代今右衛門は、染付で描いてもよさそうなところにあえて一手間二手間かけて、主文様を引き立たせるためにこの「墨はじき」の技法を使う。そこから独自の「藍色墨はじき」「墨色墨はじき」「層々墨はじき」「雪花墨はじき」など新たな技法を生み出し、高い品格と格調を醸し出す世界に類を見ない色絵磁器を創り出しています。
2014年に「色絵磁器」で要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。