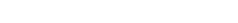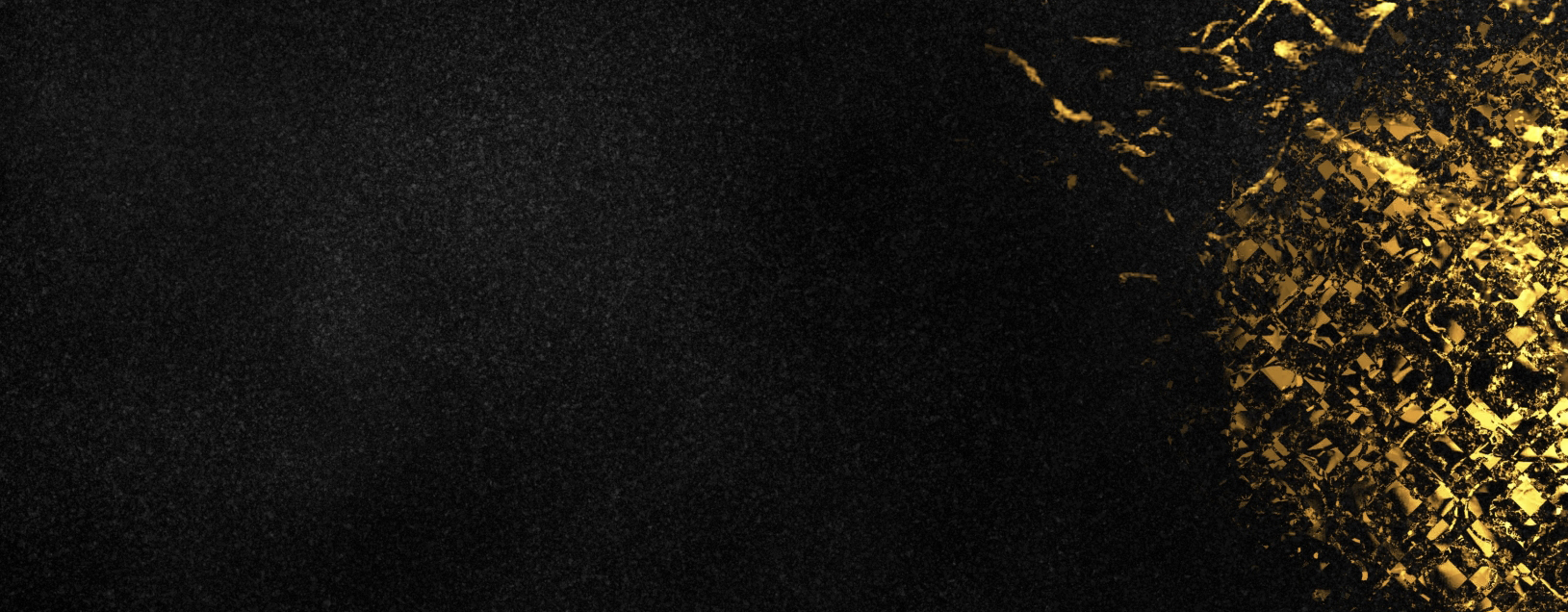
お知らせnews
2023.02.28
◇ 作家紹介 ◇ 加藤孝造
加藤孝造(かとうこうぞう)
1935年 岐阜県に生れる。
1970年 多治見市星ケ丘に半地下式単室穴窯を築く。
1972年 可児市久々利平柴谷に穴窯と登窯2基を築く。
2010年 「瀬戸黒」で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
瀬戸黒は桃山時代に現在の岐阜県大萱周辺で焼かれた焼き物です。
その独特の漆黒は、焼成中に釉薬の溶け具合を見計らい、鉄製の長いはさみで引き出して常温まで急冷させることにより、釉薬中に含まれている鉄分が黒色化して生まれたものである。別名として、その技法から「引き出し黒」、天正年間(1573~1593)より焼かれたことから「天正黒」とも呼ばれます。引き出すタイミングを見計らう勘と、炎に対する気迫が必要不可欠であり、一度に窯詰めできる数は15個程度しかなく、作られる数が限られる上に高度な技術を必要とされる焼き物です。
加藤孝造ははじめ洋画家を目指していました。高校卒業後、岐阜県陶磁器試験場にて五代加藤幸兵衛に陶芸の指導を受けまます。その後、陶芸展などでの入選・受賞を重ね、1970年に同試験場を退職して独立する。試験場勤務中には、実作活動をするだけでなく、主任技師として玉置保夫らを指導しています。
桃山時代茶陶の再興を遂げた荒川豊蔵との出会いにより、多大な影響を受け、原始的な穴窯を築き、手回し轆轤による制作を行うようになります。瀬戸黒以外にも「志野」「黄瀬戸」「鉄釉」などをすべて穴窯で薪を使って焼成しました。
瀬戸黒は桃山時代に生み出された技法で一度廃れましたが、人間国宝の荒川豊蔵によってよみがえり、加藤孝造に受け継がれています。その豊かな造形と、独自の緋色など、桃山古作に迫る作品は国内外でも高く評価されています。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。