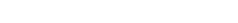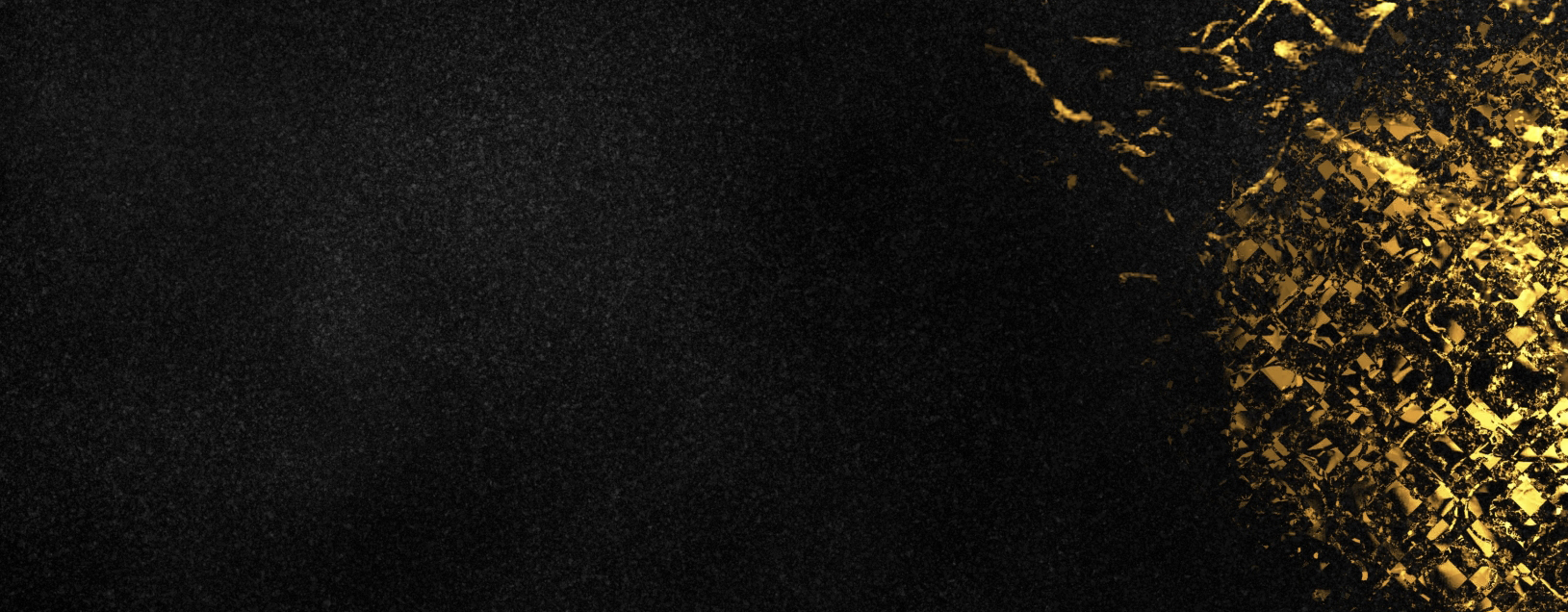
お知らせnews
2023.03.01
◇ 作家紹介 ◇ 藤原雄
藤原雄(ふじわらゆう)
1932年 岡山県備前市に生まれる。
1955年 人間国宝となる父・藤原啓に師事する。
1965年 棟方志功と共ににアメリカ・ダートマス大学の客員教授を務める。
1996年 「備前焼」の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
藤原雄は備前の陶芸家で人間国宝となった藤原啓の長男として岡山県備前市に生まれる。視力が右目は0.03、左目は全く見えないというハンディがあったが、健常者同様に進学する事に父親はこだわり続けたという。父がそうであったように文学や音楽に熱中するといった多感な青年時代を過ごし、大学卒業後は一時出版社に勤務するが、父の看病のため岡山へ戻る。父の病気全快後、その助手として備前焼の修行を始める。
小山富士夫を陶芸の美学の師、父の友人である北大路魯山人には陶芸の哲学の師と仰ぐ。雄が形にこだわって作っていた器を見て、魯山人はまだやわらかい口のところをひょいとつまんでみせたという。また川喜多半泥子、藤本能道、田村耕一や裏千家家元の千宗室匠他、自ら認める食通であることから各国のシェフ等各界の人々とも親交を暖め、その美学を深めていった。
アメリカ、カナダ、メキシコ、スペイン等の国々を廻り、各地で備前焼講座や個展を開催、同時に米国コロンビア大学における第1回国際工芸家会議で日本代表として備前焼の解説を行うなど、海外へ広く備前焼を紹介した。
茶陶としての現代備前陶という認識から出発した雄は、備前の土味を生かし、穏やかで明快な器形に削ぎや透かし、箆目、線彫で作家の作為性を加味した作風を確立し、とくに壷の制作に焦点を絞り、どっしりとした豪放な壷で新境地を開拓した。
藤原雄は「時代の推移に安易に迎合するのではなくて、時代の変化は感じながらも、普遍的な美しさ、一万年前も一兆年後も変らない価値をめざしていこう。そこにあたたかさとか、やさしさとか、強さとか、豪放さとか、そういうものを想像させる焼物をつくらなければいけない。」それが陶芸家の使命であると語っている。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。