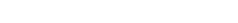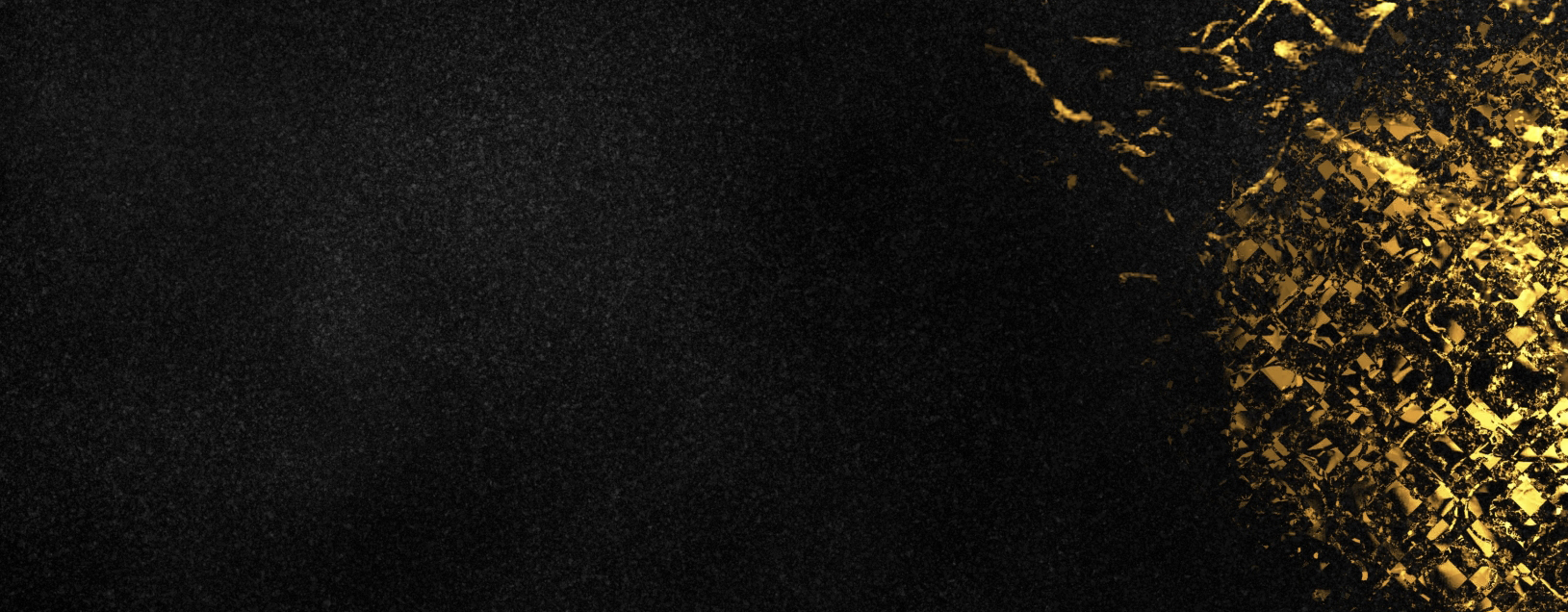
お知らせnews
2023.03.21
◇ 作家紹介 ◇ 赤地友哉
赤地友哉(あかじゆうさい)
1906年 石川県に生まれる。
1922年 塗師・新保幸次朗に師事する。
1928年 塗師・渡辺喜三郎に師事する。
1930年 独立する。
1974年 「髹漆(きゅうしつ)」で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
髹漆(きゅうしつ)は木、竹、紙などの下地に漆を塗る技法のことで、漆芸の最も基本となる技術であり、漆芸技術の中では最も古いといわれている技法です。
赤地友哉は石川県金沢市にヒノキや杉を加工する桧物師・赤地多三郎の三男として生まれます。16歳で金沢市の塗師・新保幸次郎に師事し、5年余りの修業の後、髹漆を始める。また遠州流の吉田一理に茶道を学ぶ。その後、上京し東京で随一の塗師と称された渡辺喜三郎に入門する。遠州流家元小堀宗明に茶道も学び、遠州流にちなみ友哉と号する。
独立後、京橋や日本橋で茶器などの制作につとめるかたわら、6ケ月間蒔絵師植松包美のもとで徳川本源氏物語絵巻を収める箪司の髹漆に従事し、蒔絵についても多くを学びました。
これまで人間国宝に認定された漆芸家の多くは、下地を形成した後に模様などを作る加飾の技法の保持者として認定されていますが、赤地友哉はそもそもの髹漆という下地を作る技法で認定されています。
またヒノキなどの薄板を曲げて楕円形の容器を作る「曲輪造」の技法も開発し、多彩なフォルムを作り出すと共に、曲輪をまとめて塗り固める捲胎という新手法も編み出しました。それまでの漆器は四角いものが多かったが、この曲輪造により、漆芸をより変化に富んだものにし、大きな功績として讃えられています。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。