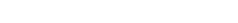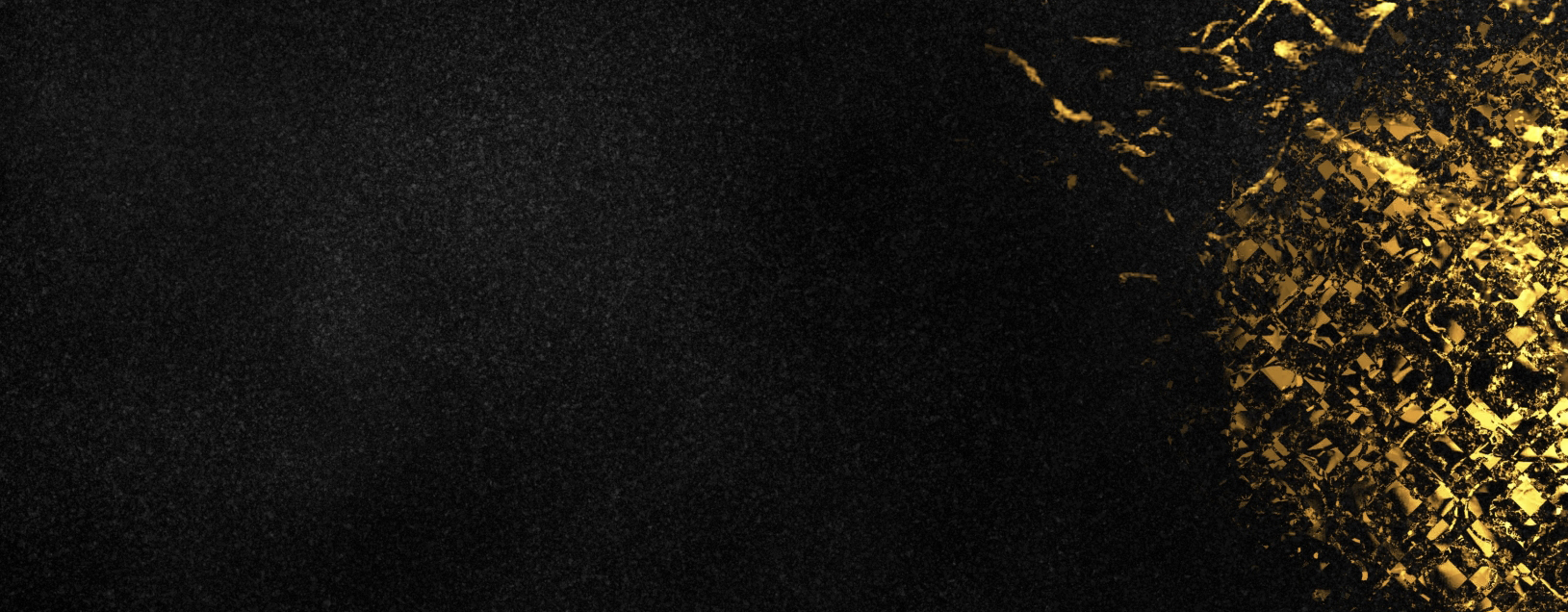
お知らせnews
2023.03.23
◇ 作家紹介 ◇ 塩多慶四郎
塩多慶四郎(しおたけいしろう)
1926年 石川県に生まれる。
1964年 蒔絵作家・勝田静璋に師事する。
1980年 東大寺昭和大納経「華厳経納入箱」を制作。
1992年 東大寺南大門阿形仁王像大修理に際して「胎納仁王経納入箱」を制作。
1993年 正倉院宝物「漆彩絵花形皿」の模造制作。
1995年 「髤漆」の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
塩多慶四郎は石川県輪島市の輪島塗塗師・角野勝次郎の四男として生まれる。3歳のときに母の実家である塩多家の養子に入る。塩多家も江戸時代から三代続く輪島塗塗師である。
小学校卒業後、養父塩多政のもとで輪島塗の修行を始める。終戦後、輪島へ復員し家業の塗師を手伝います。塩多漆器店四代目を継ぎ、本格的に輪島塗に携わり始め、蒔絵作家である勝田静璋について蒔絵を学ぶ。
文化庁・日本工芸会共催による技術伝承者養成事業に参加した時に、生涯の師と仰ぐ蒔絵の人間国宝である松田権六と出会い、松田の「塗りと形が良ければ加飾などいらない」との示唆に触発され、漆塗りの持つ本当の美しさを追求することになったという。
髹漆とは漆芸技法の根幹となる「塗り」の技術で、漆芸技法のなかではもっとも古い技法だといわれています。漆を塗る素地選びから下地工程、上塗り、仕上げまで幅広く関わる技法であり、木・紙・竹など様々な素地の特色を見極める経験や知識、素地の魅力を活かす高い技術が求められます。
塩多慶四郎はただ単に伝統的な方法で漆を塗るのではなく、和紙や麻布を素地に使い、それを漆で塗り固める技法を用いたため、出来上がった作品には深い光沢が見られます。また、東大寺南大門での修理や正倉院宝物の模造制作などを通じて日本の漆芸の保護に貢献したことが高く評価されました。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。