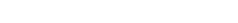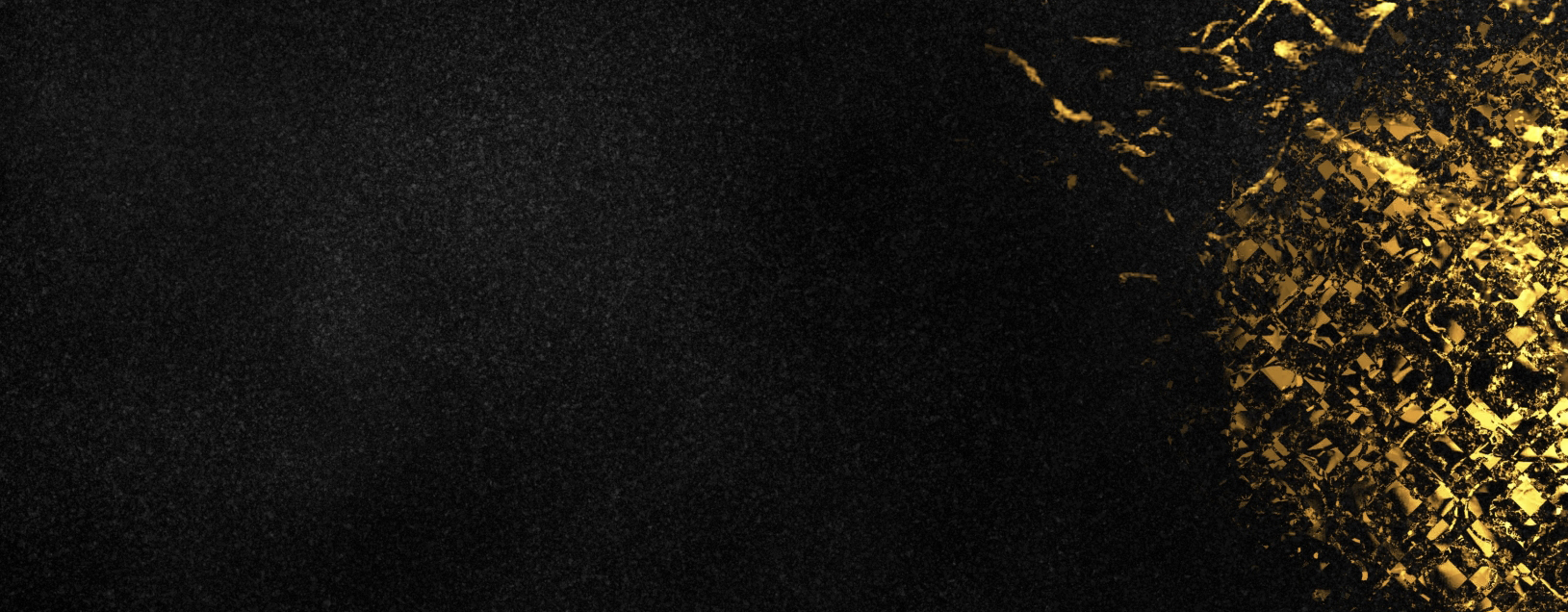
お知らせnews
2023.05.10
◇ 作家紹介 ◇ 早川尚古斎
早川尚古斎(はやかわしょうこさい)
早川尚古斎は江戸時代(文化12年)から続いている大阪の竹工芸家の名称で、その竹工芸技法は一子相伝で伝えられており当代は五代目となります。
初代早川尚古斎は福井県の出身で、京都にあった竹籠師で修業を積んでその後、大阪に移り「尚古斎」と号す。その作風は唐物写し中心の籠の世界に独自の創作性を織り込み、その技術力と完成度が認められ「浪華の籠師」と称されます。
二代早川尚古斎もまたその伝統を守りながら竹工芸技術を磨きます。襲名の8年後、45歳で逝去したため制作期間が短く、作品も少ない。
三代早川尚古斎は初代の五男で、「早川尚斎」の号で主に活動の場を東京に移し活躍します。実兄である二代が亡くなったのを機に大阪に戻り、三代を襲名します。自由な表現の荒編みなどに卓越し、竹籠の技を美術工芸の分野まで引き上げ、その名を高めました。
四代早川尚古斎は三代の長男で、代々早川家に伝わる基本形を修得しただけでなく、確かな技術を駆使して方円籃などの新しい籃花入を創出します。1945年戦災に遇い京都に転居します。
五世 早川尚古斎
1932年 大阪府に生まれる。
1945年 空襲により京都市に転居する。
1951年 父・四代尚古斎に師事する。
1977年 五代尚古斎を襲名する。
2003年 「竹工芸」の重要無形文化財保持者に認定される。
五代早川尚古斎は四代尚古斎の長男として大阪府に生まれます。本名は修平。高校卒業後、父のもとで修業に入り、竹工芸技術を基礎から学びます。その指導は厳しく「見てもわからんもんは、聞いてもわからん」と言われ、時には父が編んだ作品をほどき、独習し技術を会得しました。
早川尚古斎が代々得意とした鎧組花籃、そろばん粒形花籃、興福寺形牡丹花籃は、こうして五代まで受け継がれていきます。
また「切込透」という伝統的な鎧組(幅の広い竹材を揃えて組む)を基本として幅広の材を部分的に細かく削り、幅の広いところと狭いところを組み合わせることにより透かし文様が表れる組み方を考案するなど、伝統を踏まえた上での新たな試みが高く評価され、後年になると組技法の作品を多く手がけ「組の早川」と称されます。
また日本文化を海外に紹介する活動を行っており、イギリスの大英博物館では展覧会を開いたりアメリカで個展や講習会の場を持ち、海外の人たちと積極的に交流をはかりました。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。