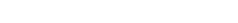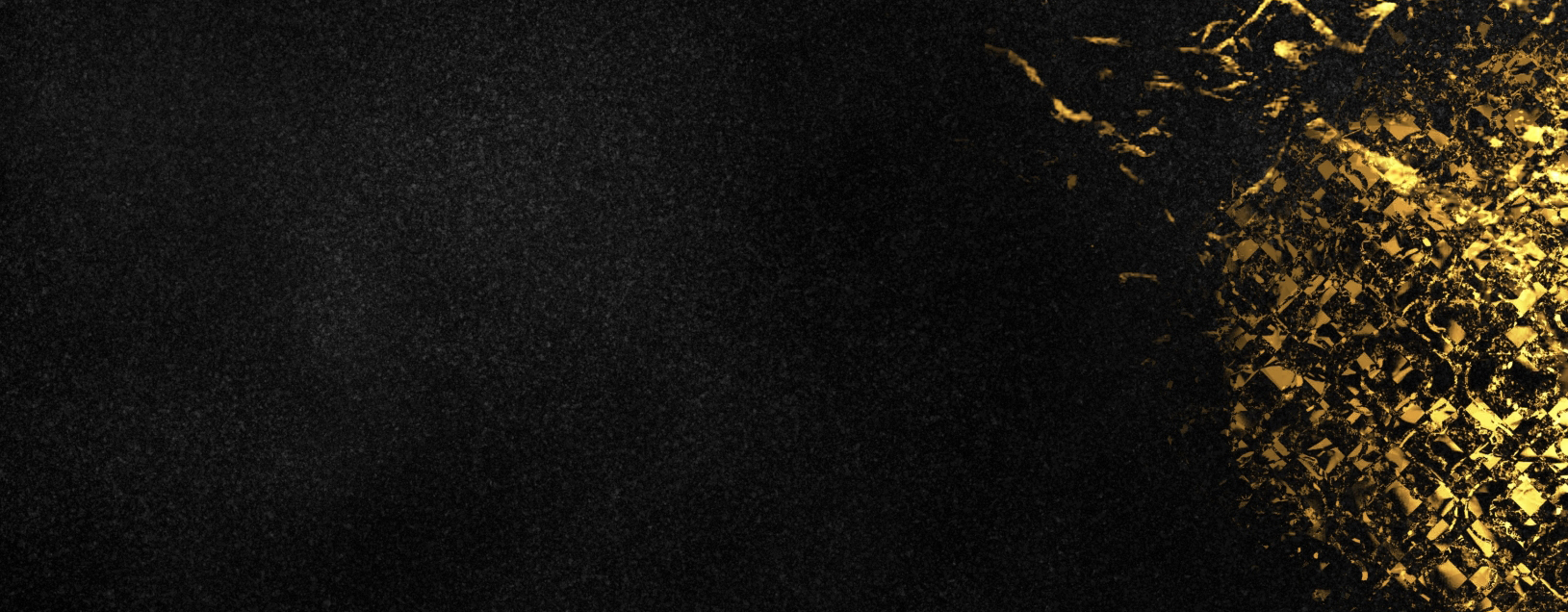
お知らせnews
2023.05.14
◇ 作家紹介 ◇ 黒田辰秋
黒田辰秋(くろだたつあき)
1904年 京都府に生まれる。
1924年 民芸運動に加わる。
1927年 上賀茂民芸協団を設立する。
1968年 皇居新宮殿の拭漆樟大飾棚、扉飾、椅子、卓を制作する。
1970年 「木工芸」の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。
黒田辰秋は京都市で塗師屋を営む黒田亀吉の六男として生れる。小学校卒業後、父の仕事場で木工芸や漆芸を独学で学ぶ。15歳で一時蒔絵師に就くが、健康を害してこれを止め、以後独学を続ける。この頃、制作から塗りまでの木工芸の一貫作業を目指して木工も独学した。また、河井寛次郎の講演に感銘を受け、柳宗悦らの民芸運動に加わる。
技術の基礎を固めた20代の頃は、朝鮮の木工品に学ぶところが大きく、透明漆を塗り木目を生かして重厚な仕上がりを見せる拭漆や、朱漆、黒漆、白蝶貝等による螺鈿などの技法を用い、大量の木工家具や装飾品等を制作する。また本の表題や扉絵、挿絵なども手がけている。後年は、青く光るメキシコ産のアワビ貝を用いた耀貝(ようがい)螺鈿の技法を確立します。
黒田辰秋は「その木の性格を、そのまま生かそうと、自然にやってきただけ」と語り、漆や螺鈿で仕上げた茶器などの小品から、椅子や飾り棚など力強い大作まで、幅広く木漆の仕事を展開し、きわめて独創的で、造形力に富んだ傑作を数多く残しています。
木質の持つ美を極力生かし、伝統に学び民芸運動にも参加する一方、卓越した技によって他に類を見ない独創的かつモダンなその作品は、白洲正子・黒澤明といった数々の文化人からも愛好され、志賀直哉をして「名工中の名品」と言わしめた。また宮内庁からも家具の製作を依頼されるなど、まさに日本の手仕事を代表する一人である。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪南美術会館では、骨董品・美術品の幅広いジャンルのお買取りを随時受け付けております。
お気軽にお問い合せ・ご相談いただければ幸いです。